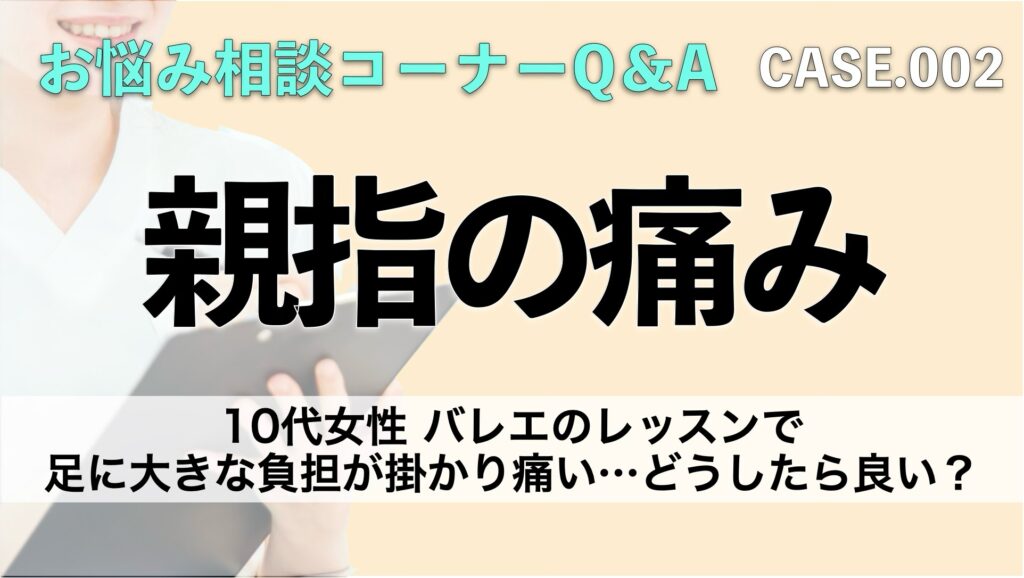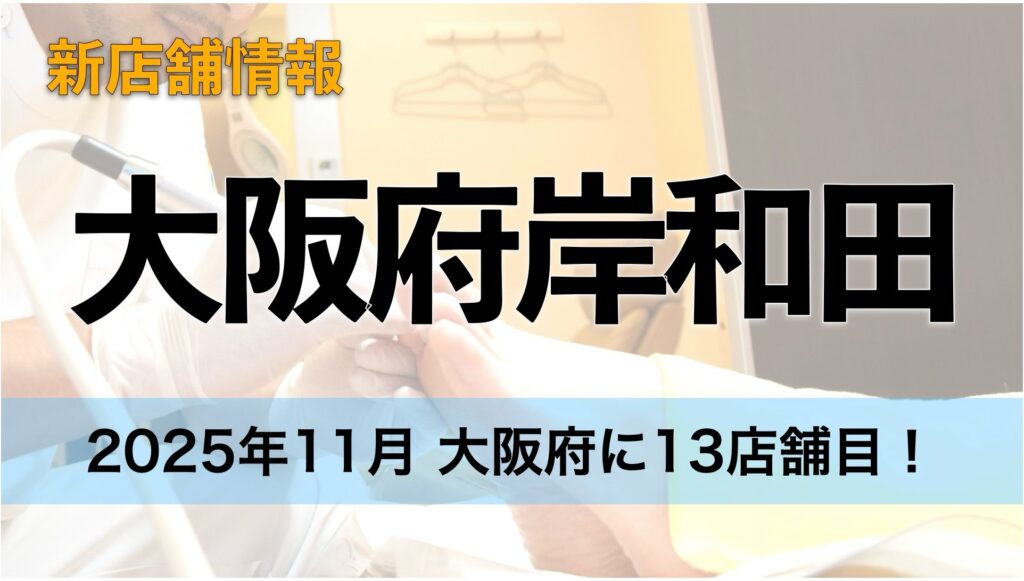巻き爪にお悩みの方へ|フットケア Q&A で安心解決!
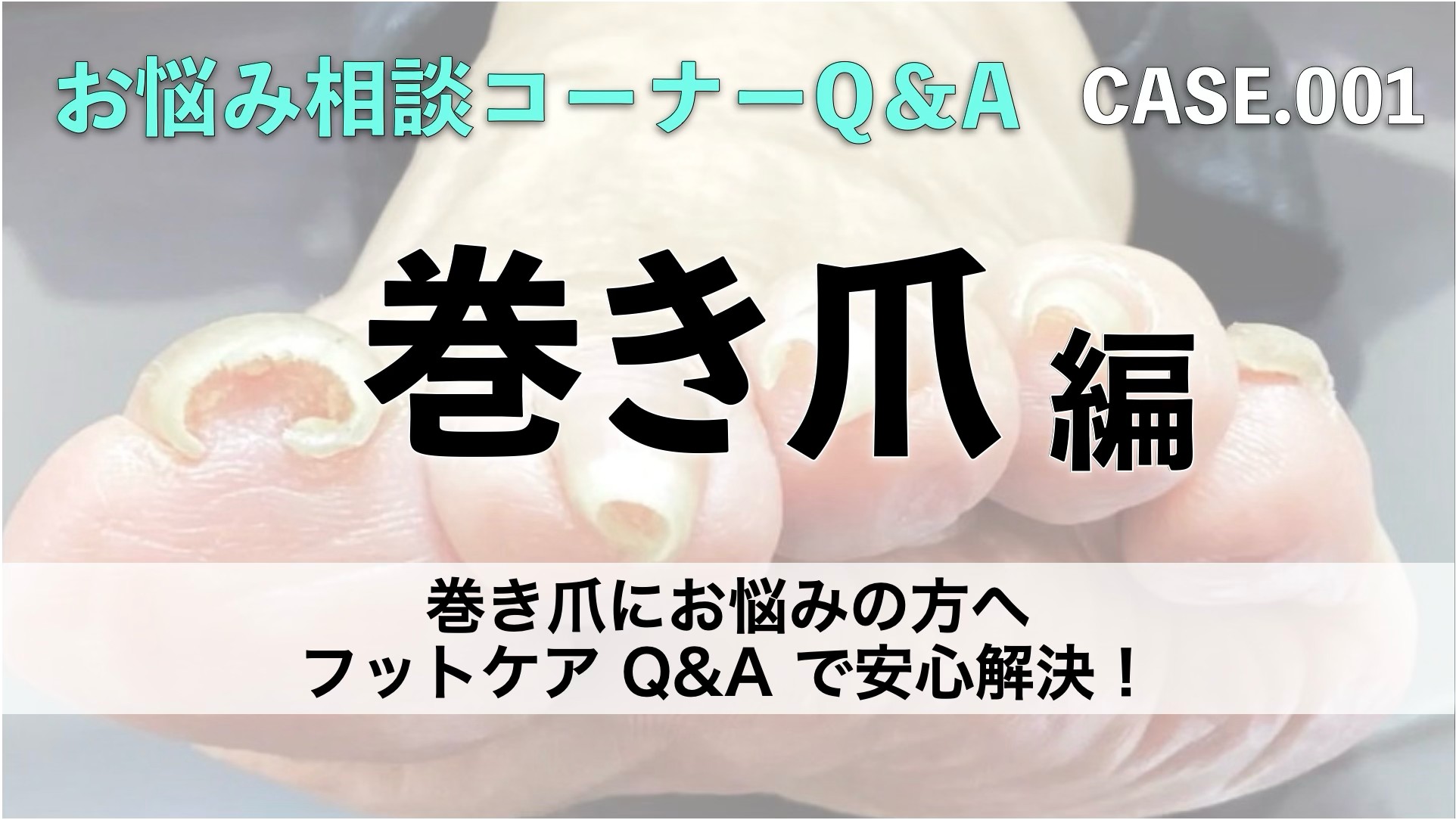
巻き爪の悩みを解決!フットケア専門家によるよくある質問 Q&A
巻き爪は、足の親指に多く見られ、爪の端が皮膚に食い込むことで違和感や炎症を引き起こすトラブルです。「どこに相談したらいいの?」「どうやってケアすればいいの?」と迷う方も多くいらっしゃいます。
このページでは、フットケアの専門家が巻き爪に関するよくあるご質問に丁寧にお答えしています。早めの対処で快適な足元を取り戻しましょう。
【Q&A】
Q1. 巻き爪を放置するとどうなる?
回答はこちら 👈
巻き爪は軽度であっても放置してはいけません。初期段階では「靴を履いたときに少し痛む」「歩くと違和感がある」など軽い症状で済むことが多いですが、放っておくと徐々に悪化します。
巻いた爪が皮膚に食い込み、炎症や化膿を引き起こすことがあります。さらに進行すると、皮膚が盛り上がり「肉芽(にくげ)」と呼ばれるぶよぶよした組織ができ、激しい痛みを伴います。この状態になると、靴を履けない、歩けないといった日常生活への影響が大きくなります。
また、痛みを避けるために無意識に歩き方が変わり、膝や腰に負担がかかって全身のバランスが崩れることもあります。高齢者では転倒のリスクも高まります。
さらに重症化すると、保存的なケアでは改善できず、外科的な手術(部分的な爪の除去や、爪母の焼灼処置)が必要になることもあります。
巻き爪は自然に治ることはほとんどありません。痛みが軽いうちに、フットケア専門家や医療機関に相談することで、手術を回避し、矯正による改善が可能になります。
Q2. 巻き爪の原因ってなに?
回答はこちら 👈
巻き爪は体質や遺伝も影響しますが、多くの場合は生活習慣に原因があります。特に多いのは次の 3 つです。
1 つ目は「爪の切り方」です。爪の角を丸く切ったり、深爪をすると、爪が皮膚に食い込みやすくなり、巻いて生えてくるようになります。正しい切り方は「スクエアカット」といって、爪の先端をまっすぐに切り、角を少し整える程度にするのが理想です。
2 つ目は「足に合っていない靴」。つま先の狭い靴や、ヒールの高い靴、サイズが合わない靴を履き続けると、爪を横から圧迫し、巻き爪が進行しやすくなります。
3 つ目は「歩き方」です。足指を使わず、かかと重心やペタペタとした歩き方をしていると、爪に適度な上からの力が加わらず、爪が内側に巻いていく力が強くなります。
その他にも、加齢による水分不足、爪の病気(乾癬や白癬など)、遺伝的に細くて湾曲しやすい爪なども原因となります。
巻き爪を予防するには、爪の正しい切り方を知ること、足に合った靴を履くこと、そして足指をしっかり使った歩行を意識することが大切です。
Q3. 巻き爪って自分で治せるの?
回答はこちら 👈
巻き爪は、軽度であれば市販の矯正テープやプレートを使って自分でケアすることが可能です。また、正しい爪切りや保湿、足に合った靴を選ぶことでも悪化を防げる場合があります。
ただし、セルフケアには限界があります。特に「歩けないほど痛い」「爪の周りが赤く腫れている」「膿が出ている」「肉芽ができている」といった症状がある場合は、自分で治そうとせず、早めに専門家に相談することが大切です。
無理に爪を持ち上げたり、深く切り込んだりすると、出血や感染を引き起こし、かえって症状を悪化させてしまう可能性があります。
現在では、痛みの少ない巻き爪矯正技術も多数あり、手術をせずに改善できるケースも増えています。巻き爪は「放置せず」「無理をせず」「早めに相談する」ことが、最も安全かつ効果的な対応法です。
Q4. 巻き爪におすすめの靴ってある?
回答はこちら 👈
巻き爪の悪化を防ぐためには、靴選びが非常に重要です。爪にかかる圧力や摩擦が、巻き爪の進行に直接関係しているからです。
まず避けたいのは、つま先が細く、硬い素材の靴。パンプスやポインテッドトゥ、先端のとがった革靴などは、足指を圧迫し、爪を内側に巻き込む力を強めてしまいます。
逆に、巻き爪予防におすすめなのは以下のような靴です:
- つま先にゆとりがある(足指が自由に動く)
- 柔らかくクッション性がある
- かかとがしっかりホールドされる
- 足にぴったりフィットして脱げにくい
また、「靴ひもがしっかり締められる」スニーカーもおすすめです。ひもを適切に結ぶことで、足が前滑りせず、指先への圧迫を減らせます。
インソールやフットケア用の中敷きを使って足裏の圧力を分散することも、巻き爪の予防に効果的です。靴選びに迷ったときは、フットケア専門店で足の形に合った靴を選んでもらうのが理想的です。
Q5. 痛くない巻き爪の矯正方法はある?
回答はこちら 👈
「巻き爪の矯正=痛い・怖い」というイメージを持つ方は多いですが、現在では痛みの少ない矯正方法が多数開発されています。特に、手術をせずに爪の形状を整える保存的な矯正法が主流になっています。
代表的な「痛くない矯正方法」は以下のようなものです:
- プレート矯正(B/S スパンゲ、3TO など):形状記憶の特殊なプレートを爪の表面に貼り、内側から爪を引き上げる方法。痛みがほとんどなく、見た目も自然。
- ワイヤー矯正(VHO 式など):専用ワイヤーを爪の両端にかけて力をかける方法。やや技術が必要ですが、重度の巻き爪にも対応できます。
これらの矯正法は、爪の厚みや巻きの度合い、生活スタイルなどに応じて使い分けられます。どちらも麻酔やメスを使わないため、日常生活をしながら施術が可能です。
痛みが不安で受診を迷っている方こそ、まずは「手術ではない方法がある」という事実を知っていただきたいです。早期に対応すれば、1 回の施術でも効果を感じられることがあります。
Q6. 巻き爪に市販の矯正グッズは効果ある?
回答はこちら 👈
近年、ドラッグストアやネットショップではさまざまな「巻き爪矯正グッズ」が市販されています。テープタイプ、プラスチック製の矯正器具、ワイヤー型など種類は豊富で、軽度の巻き爪に対しては一定の効果が期待できます。
主な市販グッズには以下のようなものがあります:
- 巻き爪矯正テープ(爪を引き上げるように貼る)
- プラスチック製のリフター(爪の先端に装着)
- 弾性ワイヤー(自己装着型)
これらは使い方さえ正しければ、一時的な痛みの軽減や爪の形の補正に有効です。
ただし、次のような場合は市販グッズでは対応しきれません:
- 爪の食い込みが深い・出血や化膿がある
- 痛みで歩行が困難
- 矯正してもすぐに元に戻る
また、装着方法を間違えると逆効果になることもあるため、説明書をよく読み、安全を確認したうえで使用する必要があります。
市販品はあくまでも「応急処置・予防的なセルフケア」として活用し、症状が強い場合はフットケアの専門家や皮膚科などに相談しましょう。
Q7. 爪の切り方で巻き爪になるって本当?
回答はこちら 👈
はい、本当です。実は、爪の切り方は巻き爪の最大の原因の一つといっても過言ではありません。誤った切り方によって、爪が皮膚に食い込みやすくなり、巻きやすい形状に育ってしまうのです。
特に注意が必要なのが次の 2 つです:
- 深爪(短く切りすぎる)
- 丸く切る(ラウンドカット)
爪の角を丸く削ると、皮膚が爪を押し返すスペースがなくなり、次に伸びてくる爪が皮膚の中へ食い込むように成長してしまいます。これは陥入爪(かんにゅうそう)と呼ばれる状態で、炎症や出血、肉芽形成の原因にもなります。
では、正しい爪の切り方とは?
それは「スクエアカット」と呼ばれる方法です。爪の先端をまっすぐに切り、角は軽く整える程度にとどめます。こうすることで、爪が横から皮膚に食い込みにくくなり、巻き爪の予防につながります。
爪切りは日常の何気ない習慣ですが、巻き爪対策においては最も重要なセルフケアの 1 つです。とくに成長期の子どもや高齢は、爪の状態に注意して切るよう心がけましょう。
Q8. 巻き爪の手術は痛い?再発する?
回答はこちら 👈
巻き爪の手術に対して「怖い」「痛そう」と感じる方は多いと思います。しかし実際には、麻酔を使用して行われるため、施術中に強い痛みを感じることはほとんどありません。
巻き爪手術にはいくつか種類がありますが、一般的に行われているのは以下の方法です:
- フェノール法(部分的な爪母の除去)
- くさび状切除術(食い込んだ爪の一部を除去)
これらの手術は、巻いて皮膚に刺さっている爪の根元を焼灼・除去することで再発を防ぐというものです。処置後は 1~2 週間程度で日常生活に戻ることができます。
ただし、「手術をすれば必ず治る」わけではありません。術後に再発するケースもあります。とくに以下のような方は注意が必要です:
- 爪の生え方や形が元から巻きやすい
- 靴や歩き方の癖を改善していない
- 深爪などの原因が変わっていない
根本的な原因(靴・歩き方・生活習慣)を改善しなければ、再び同じ場所に巻き爪が起こることがあります。
手術は有効な選択肢ですが、保存的な矯正法(プレート・ワイヤーなど)でも改善するケースが多く、早期の相談が大切です。手術を受けるかどうかは、症状の程度と生活スタイルに応じて、専門家と相談して決めることをおすすめします。
Q9. 巻き爪で歩けないほど痛いときはどうすれば?
回答はこちら 👈
巻き爪が悪化すると、靴を履けない・歩けないほどの強い痛みが出ることがあります。これは爪が皮膚に深く食い込み、炎症や感染を起こしている状態で、緊急性のある状態です。
そんなときの対処法は、以下の通りです:
【1】無理に爪を切らない
痛みが強いときに自分で爪をいじると、出血や感染を招く可能性があります。自己処理は NG です。
【2】靴を履かず、患部を保護する
柔らかいサンダルや、つま先が当たらないスリッパなどを使用し、足に刺激を与えないようにしましょう。
【3】患部を冷やす(炎症時のみ)
赤みや腫れがある場合は、清潔なタオルで冷やすことで痛みが一時的に和らぎます。
【4】すぐに専門家へ相談を
歩行困難な巻き爪は、フットケア専門店や皮膚科・形成外科での処置が必要です。炎症が強い場合は、抗生剤の投与や局所処置が必要になることもあります。
※応急処置に限界がある理由
巻き爪は、放置すればするほど悪化し、処置が難しくなります。応急処置で一時的に痛みが引いても、根本的な解決にはなりません。早めに専門家の診察を受け、再発防止のケアや矯正を始めましょう。
Q10. 高齢者の巻き爪ケアはどうすればいい?
回答はこちら 👈
高齢者は、巻き爪になりやすく、治りにくい傾向があります。加齢による爪の乾燥・変形・血行不良に加えて、歩行能力の低下や自己処理の難しさが原因です。また、糖尿病や認知症などの持病がある場合、小さな傷が大きな炎症や感染につながるリスクも高くなります。
高齢者の巻き爪ケアで重要なのは、次の 4 つのポイントです:
① 正しい爪切りを定期的に
スクエアカットを基本とし、深爪にならないよう注意します。自分で切れない場合は、フットケア専門サービスや訪問フットケアを利用するのも有効です。
② 足に合った靴を選ぶ
つま先の締めつけが少なく、脱げにくい安定した靴を選びます。転倒防止の観点でも、靴選びは非常に重要です。
③ 歩行や運動のサポート
足指を使った歩行や軽い運動は、巻き爪予防に有効です。必要であればインソールや歩行補助具の活用も検討しましょう。
④ 異変があれば早めに受診を
「赤い・腫れている・痛がっている」などのサインが見られたら、放置せず早期に専門機関に相談を。感染を防ぐことが命に関わることもあります。
高齢者の足は「生活の質」に直結します。巻き爪は見た目以上に深刻な問題につながるため、家族や介護職の方も巻き爪への理解と支援が重要です。
Q11. 子どもに巻き爪ってできるの?
回答はこちら 👈
はい。意外に思われるかもしれませんが、成長期の子どもにも巻き爪はよく見られます。特に小学生〜中学生の時期に、足のサイズが急激に変わることで靴が合わなくなったり、運動量の多さで足指に強い圧がかかることが影響します。
子どもに巻き爪が起きやすい原因
- 靴のサイズが小さい or 大きすぎてズレる
- 爪の切りすぎ(深爪)• 運動時の足指への強い圧力
- 足指の変形(浮き指・外反母趾など)
子どもの巻き爪対策
- 正しい爪の切り方を親が教える(丸く切らない・深く切らない)
- 定期的に靴のサイズを確認し、ジャストサイズを選ぶ
- 足指の運動や体操で足の使い方を覚える
痛みを訴える・赤くなっている・触れると嫌がるといった場合は、自己判断せずに医療機関やフットケア専門店に相談することが大切です。
特に子どもの足は発育途中なので、早期に対応すれば変形や巻き爪の癖を予防できる可能性が高いです。親子での正しいフットケア習慣が、将来の足トラブルを防ぎます。
Q12. 巻き爪と病気の関係はある?(糖尿病や皮膚病など)
回答はこちら 👈
巻き爪は、いくつかの病気と深い関わりがあります。特に注意が必要なのは、以下の疾患をお持ちの方です。
■ 糖尿病
糖尿病の方は、末梢血流の低下や神経障害によって痛みに気づきにくく、巻き爪が進行しやすい傾向があります。また、傷ができると感染しやすく、重症化すれば壊疽(えそ)や切断のリスクもあります。
→ 巻き爪の兆候があれば、医療機関と連携しながらのフットケアが必須です。
■ 乾癬(かんせん)や白癬(はくせん)
- 乾癬性爪疾患:爪の変形や肥厚が見られ、巻き爪を引き起こしやすくなります。
- 白癬菌(爪水虫):爪がもろくなり、巻いたり厚くなったりします。
→ このような皮膚疾患がある場合は、皮膚科での治療と並行して、爪の形状ケアが重要です。
■ 甲状腺疾患・リウマチ・腎疾患など
これらの疾患によっても、血流障害・代謝の変化・爪の成長異常が起き、巻き爪につながることがあります。
【まとめ】
巻き爪を単なる「爪の変形」と考えるのではなく、全身の健康とつながった症状の一つとしてとらえることが大切です。とくに基礎疾患がある方は、自己判断ではなく、専門家の定期チェックを受けることが巻き爪予防の第一歩になります。
◆フットケア専門店
▶︎ お近くの店舗を探す 👈
◆ご相談について
なお、足のお悩みや気になる症状がある場合は、写真を添付してご相談いただければ、状態を確認のうえ、最善の対応方法をご案内いたします。些細なことでもお気軽にご連絡ください。専門スタッフが丁寧にサポートいたします。
▶︎ お悩み相談コーナー 👈
 監修:石田麻美 | ・看護師 ・一社)日本フットケア足病医学会 賛助会員 ・一社)国際コメディカルアンドヘルスケア協会講師 ・シックネイルケアセラピスト® ・ドクターネイル爪革命 九州本店長 |